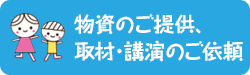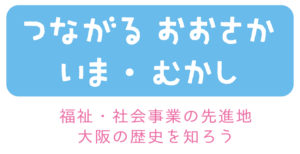
人は なさけの したにすむ
——「児童福祉の父」石井十次の大阪事業(下)
大阪は 、1890年代半ばから、東京を越え日本最大の都市となっていました。また日清戦争(1894年〜95年)後、物価が高騰。また、日本での産業革命の進展とともに、社会的格差の拡大、貧困層の増加などが大きな問題となっていました。石井十次の岡山の孤児院にも、大阪から、多くの子どもたちがやってきていました。
「孤児を生みださない社会を作ろう。そのためには、岡山での孤児の受け入れだけではなく、大都市大阪での諸問題を解決せねば」――十次の「大阪事業」がスタートします。
1907年(明治40年)、十次は「岡山孤児院」の大阪事務所を大阪駅近くの出入橋に作ります。さらに、社会の底辺で生活を共にしてこそ、当事者に寄り添った支援ができる、との信念から、1909年、7月12日(11日の予定が梅雨で延期)、大阪市南区(現在の浪速区)の「長町(名護町)」に拠点を開設します。
前回述べた、今年3月に除幕された「石井記念愛染園発祥の地 」の碑文にあったように、高津入堀川に架かる愛染橋のたもとに、夜学校、保育所、そして、同情館を開所したのです。同情館とは、無料職業紹介、宿泊施設、往診、困窮者の保護などを行う施設です。
当時、長町は、歌舞伎の人気演目「夏祭浪花鑑(なつまつり なにわかがみ)」の舞台ともなり、江戸時代から知られる、いわゆる「スラム」でした。ここで十次の大阪事業は、スタートしたのです。当時、日本最大の都市大阪における、最大の「課題蓄積地域」でした。
さて、十次の大阪事業の特徴を私なりに整理すると
――まず、「包括的」なこと。
困難を抱える子どもたちの背景には、困難を抱える家族がいます。さらに、困難を抱える地域があります。子どもだけを救えばいいということではありません。だから、教育や識字、仕事づくりなど様々な支援が必要でした。生活のさまざまな局面をささえねばなりません。
子どものための学校を作っても、この連載ですでに見た「徳風小学校」や「有隣小学校」のように、昼間働かざるをえない子どもたちには、通うことが困難です。とすると、夜学校が必要です。
夜学校や、同情館などに表れるように、十次は、子どもたちの「背景」、すなわち家族や地域環境まで見通す視点を持っていました。
また、もう一つ――
「暮らしを共にすること」
たまたま、月一回とかイベント的に支援をするだけでは、生活の種々の困難の諸相が分かりません。その地域の問題を、住民の一員として取り組み解決していくという、当時、イギリスやアメリカのシカゴなどで発展していた「セツルメント」の機能が、石井十次の大阪事業には備わっていました。
当時の「同情館」の写真を見ると面白いですよ。表にどうどうと書かれているのは「舌代」。つまり、今で言うならば「大衆食堂のメニュー」です。
でも、「メニュー」の中身は「すうどん」「めし」ではなく、「みもと引きうけ」「しごと紹介」「びょう人の世話」などです(漢字には、すべてルビが振られています)。そこで暮らしている仲間だから分かる、かゆいところに手が届く支援です。
大阪事業だけでなく、岡山孤児院も含めて、石井十次の「人を支える哲学」には、いくつかの特徴があります。
十次の言葉では、「満腹主義」です。
CPAO的に言うと「まずは、ごはん」
これは、「とにかくご飯を食べさせたらいい」とかいうなおざりの対応や、「食育が大事」という、教訓指導的なものではありません。
盗みや非行に走る、世間の眼からは「悪童たち」とみえる子どもたち。真の解決は、その子たちの「矯正」ではありません。
その子どもたちの行動の背景には、「空腹」に象徴される、社会的な貧しさがあります。それは、私たちが解決しなければならない「私たちの問題」であるはずです。なぜ、子どもたちが盗みを働くのか、「問題」とされる行動に走るのか、「まずは、一緒にご飯を食べる」ところから始まります。
そこで、子どもたちや家族の何気ない「つぶやき」を拾う。人間関係を作って行く。もちろん、おなかいっぱい食べると、子どもたちのこころも落ち着きます。
それから「家族主義」というのも、十次の理念の一つでした。
これは、「父親は父親らしく、母親は母親らしく、子どもは子どもらしく」という、「家族主義」ではありません。「子どもの成長は親の責任だ。家族でなんとかしなさい!」という意味ともまったく反対です。
十次は、「子どもを幸せにするためには、幸せな大人が隣にいることが大事」(『石井十次の残したもの』p.461)と語りました。
「大人」とは家族に限りません。家族が、周囲の地域が幸せになることが必要なのです。支援は、そこまでの視点を持たねばなりません。その中で育まれてこそ、子どもが幸せになれる――これが、十次の「家族主義」です。
また、彼の孤児院は、当時の多くの施設のように、大部屋で大人数が一緒に暮らすというものではなく、「家族」的でした。数人の子どもと世話を焼く大人がいる、いくつもの小部屋に分かれていたのです。これは、今の児童養護施設のユニット型と言われるものの考え方を先取りしていたといえるでしょう。
それからもう一つの特徴は「密室主義」。現代ではなにか、恐ろしげに響きますが、これも今の意味とは正反対です。
――子どもと話すとき、子どもの相談を受ける時には、一対一で、子どもたちの人権、プライバシーを守ることに、最大限の注意を払わねばならないと言う意味です。
十次自身は、大阪事業を始めてから、7年後に、48歳の若さで亡くなっています(腎臓病)。
しかし、大阪事業は、今のクラレや中国電力(当時は、中国水力電気会社)や大原美術館を創設した大原孫三郎が引き継ぎます。財団法人石井記念大阪愛染園となり、救済事業研究室もできます。これは、法政大学大原社会問題研究所の源流です。周産期医療・母子医療・低費診療事業の愛染橋病院も開院しました。
第二次大戦下の統制の影響を受けたり、空襲で焼けたり、紆余曲折はありましたが、大阪事業全体は、社会福祉法人石井記念愛染園として、今も、旧長町とそして釜ヶ崎で、厳然と人に寄り添っています。
「鮎は瀬に住む 鳥は樹にやどる 人はなさけの下に住む」
石井十次が、好んで口ずさんだ歌の一節です。
実は、北は、岩手の久慈の盆踊り唄、また幾度の飢饉、さらに原発事故の被害まで受けた福島県相双地域に伝わる「相馬二遍返し」、鹿児島県西薩摩「はんや節」などなど、全国の盆踊り唄、子守唄、労働歌に、同じフレーズが出てきます。
苛酷な人生、苛酷な自然にさらされながらも生きてきた人たちに愛され、口ずさまれて、日本中に広まった――そんな一節なのでしょう。
この、人々の生活に根ざしたフレーズを好んで口ずさんだところに、気取らない、そして、困った人たちとともに生きようとした、石井十次の生きる姿勢が、見事に示されているように思います。
そして、その姿勢は、多くの人たちに受け継がれ、今も、厳然と生き続けているのです。